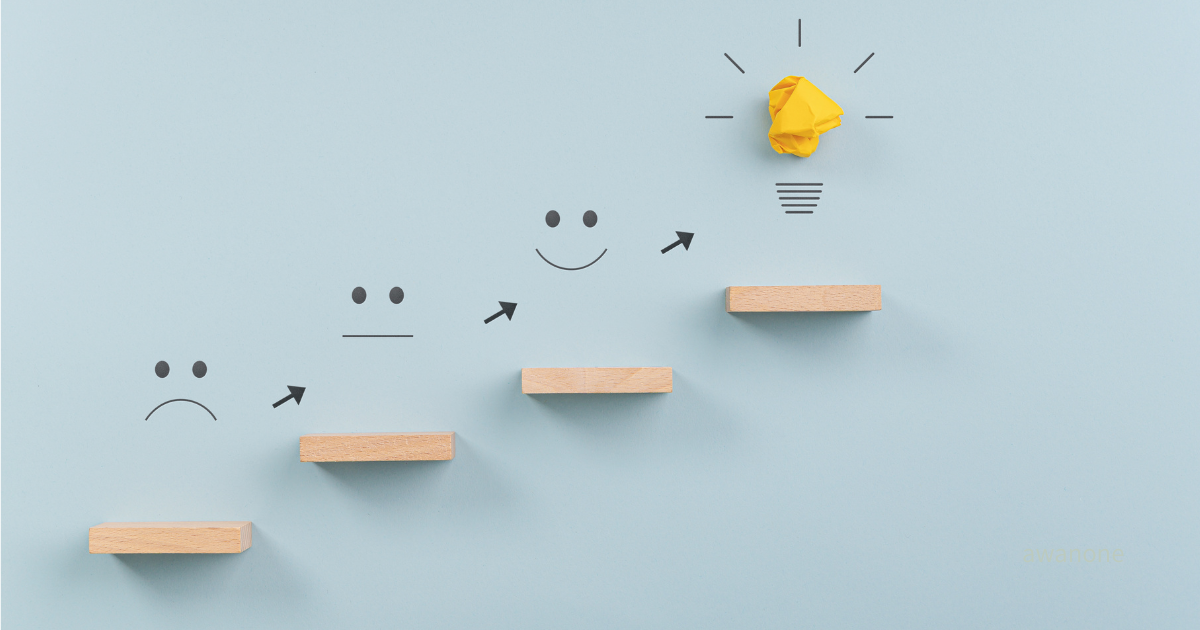はじめに:MRIの「損傷」という言葉に惑わされないで
MRI検査で「股関節唇損傷」と診断されると、多くの方は「もう壊れているのだから手術しかない」と感じてしまいます。
しかし、関節唇の損傷=痛みの原因とは限りません。
近年の研究では症状のない人の20〜30%にも関節唇の損傷が見られることが報告されています。
(参考:Register et al., Radiology, 2012)
つまり、MRIで見つかる損傷は「構造的な変化」であり、「症状の原因」とは別問題であることが多いのです。
関節唇損傷が痛みの原因とは限らない理由
股関節の痛みは、以下のような複数の要素が関与して起こることがあります。
- 関節包や靭帯の短縮・癒着
- 大腿骨頭のわずかな位置変化
- 骨盤や脊柱の可動性低下
- 深部感覚の乱れや神経の過敏化
このように、**「動き」や「神経の感受性」**が痛みに関係している場合、
関節唇を修復しても痛みが続くケースが少なくありません。
手術を受けても改善しないことがある理由
股関節唇損傷に対する関節鏡手術は、損傷部を縫合・切除することで痛みの軽減を目指します。
しかし、術後も「痛みが残る」「可動域が戻らない」という報告もあります。
手術によって構造的な問題が解消されても、
神経系の過敏や筋肉のアンバランス、体幹・骨盤の機能低下など、
機能的な要因が残っていれば、痛みの改善は限定的です。
(参考:Nepple et al., The Journal of Bone and Joint Surgery, 2015)
保存療法で変化が見られるケースも多い
最近では、**保存療法(非手術的アプローチ)**の有効性も報告されています。
例えば、
- 股関節周囲筋の再教育
- 体幹・骨盤の安定性トレーニング
- 感覚入力の改善(神経リセット)
などを継続することで、痛みや動きが改善する例が多く見られます。
関節唇自体は再生しにくい組織ですが、痛みの原因が“関節唇だけ”ではないため、
全体のバランスを整えることで十分に回復する可能性があります。
手術を検討する前に確認したい3つのポイント
- 本当に関節唇が痛みの主因か?
画像ではなく、動作・姿勢・触診などから多面的に確認する。 - 骨盤や腰椎の動きはどうか?
股関節の動きは体幹の動きと密接に関係しており、連鎖を見落とすと再発しやすい。 - 神経系の過敏化はないか?
長期間の痛みは、脳や脊髄レベルで感受性が高まる「中枢性感作」を伴うことがある。
これらを評価し、身体全体の機能を見直すことが、最も安全で確実な回復への道です。
治療室アワノネでの取り組み
当院では、股関節唇損傷と診断された方に対しても、
・神経・筋・骨格の連動評価
・体幹・骨盤の安定性の再教育
・深部感覚のリセットアプローチ
を中心に、全身的な観点から保存的アプローチを行っています。
実際、手術を検討されていた方が保存療法で痛みの軽減を実感されるケースも多くあります。
まとめ
- MRIで損傷が見つかっても、痛みの原因とは限らない
- 手術をしても痛みが残るケースがある
- 保存療法で改善する例も多い
- 全身の機能を整えることで、股関節への負担を減らせる
股関節唇損傷は、“構造の問題”だけではないという視点が大切です。
焦らず、身体全体を見つめ直すことから始めてみてください。