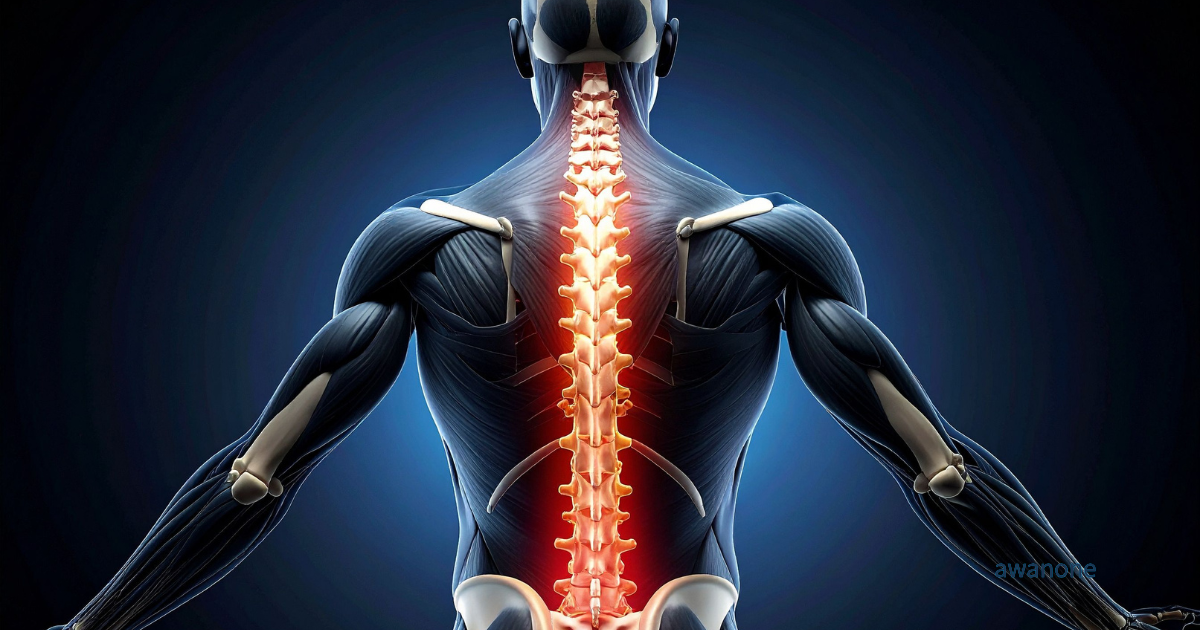〜神経の促通が鍵になる〜
変形性股関節症のリハビリというと、
「筋トレで筋肉を強くする」「ストレッチで柔軟性を上げる」
といった“動かす練習”を思い浮かべる方が多いと思います。
しかし実際のリハビリは、
その前段階――**“動かすための準備”**から始まります。
この準備を整えるかどうかが、
保存療法(手術をしない治療)の成果を左右すると言っても過言ではありません。
痛みのある体は「動かせない状態」
変形性股関節症では、
痛みや変形により次のような変化が起こります。
- 股関節まわりの筋肉が硬く緊張する
- 骨盤や体幹のバランスが崩れる
- 痛みを避けるための代償動作が増える
こうした状態では、神経と筋肉の連携が乱れ、
「正しい動きができない=動かす準備が整っていない状態」です。
このまま筋トレやストレッチを行っても、
筋肉はうまく反応せず、痛みが強くなったり疲れやすくなったりします。
リハビリの本質は「神経の促通」にある
個人的な見解として、
リハビリで最も重要なのは**神経の促通(nerve facilitation)**です。
神経が適切に働くことで、
- 筋肉がタイミングよく反応する
- 関節の動きが滑らかになる
- 姿勢やバランスが自然に整う
といった“動ける状態”が生まれます。
どんなに筋肉をほぐしても、
神経がうまく働いていなければ動作は再現されません。
そのため、リハビリとは神経を再教育するプロセスであり、
「動かす練習」ではなく「動かす準備」こそが本質なのです。
研究が示す「整えてから動かす」重要性
2022年のレビュー研究(Arokoski et al., Clinical Rehabilitation)では、
変形性股関節症の運動療法を行う前に、
関節可動域や筋の協調性を改善した群は、
そうでない群に比べて痛みの軽減・歩行能力の改善が有意に高かったと報告されています。
つまり、「整えてから動かす」ことが、
保存療法の成果を高める科学的根拠として示されています。
「ほぐす」はセルフケア、「整える」はリハビリ
筋肉をほぐすことはセルフケアとして有効ですが、
それだけではリハビリとは言えません。
リハビリとは、
神経と筋肉の反応を再構築し、正しい動きを呼び戻す作業です。
「ほぐす」は一時的な緩和、
「整える」は再教育。
ここを区別することで、リハビリの意味がより明確になります。
まとめ:神経が動きを導く
変形性股関節症のリハビリは、
筋肉を動かす練習ではなく、動かすための準備。
その準備の中心にあるのが、神経の促通です。
神経の働きを整えることで、
筋肉と関節が正しく反応し、股関節の動きが自然に戻っていく。
それが、痛みを軽減し、保存療法の成果を最大化する第一歩になります。
焦らず、まずは“神経にスイッチを入れること”。
これが、股関節を守るために最も大切なリハビリの考え方です。