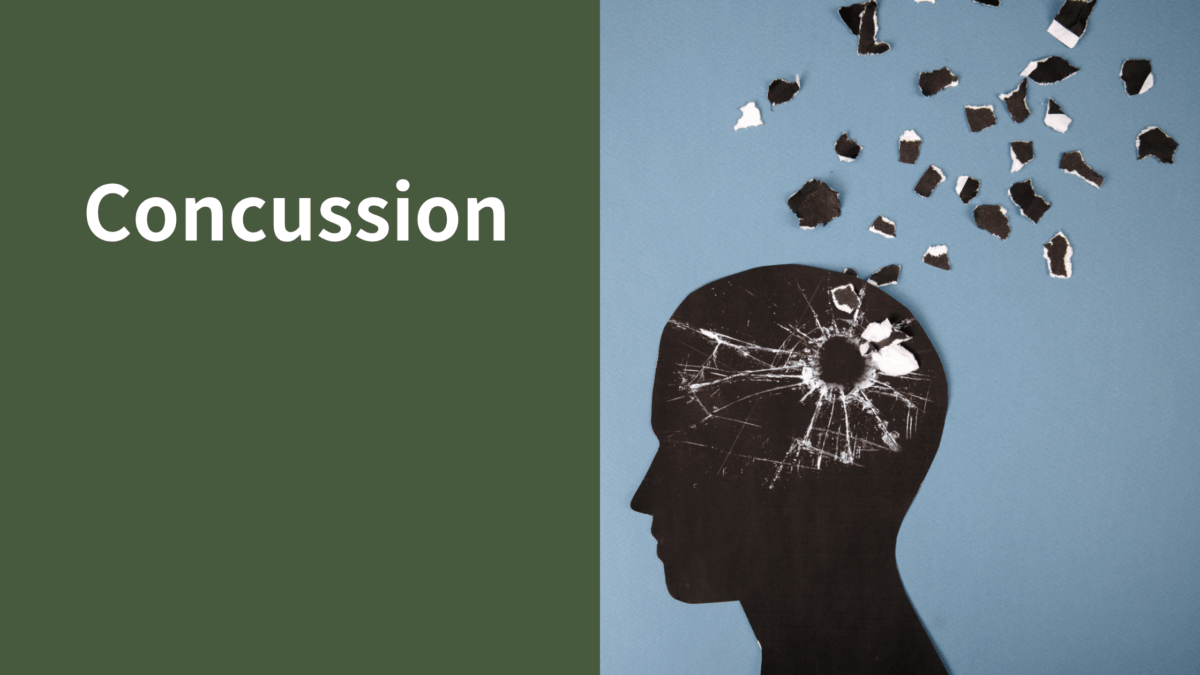脳震盪とは?「軽く頭を打っただけ」が大きな問題になることも
日常の転倒やスポーツ中の接触などで頭を打ったあと、
「すぐに動けたから大丈夫」と思っていませんか?
しかし、それは**脳震盪(のうしんとう)**かもしれません。
脳震盪とは、頭部への衝撃により脳の働きが一時的に乱れる状態のこと。
CTやMRIで異常が出ないことも多く、軽症に見えがちですが、神経の機能に深刻な影響を与えることもあります。
脳震盪で起こる主な症状|数日後に現れることも
脳震盪の症状はすぐに現れるとは限りません。
衝撃を受けてから数時間〜数日後に以下のような不調が出ることがあります。
- 頭痛、吐き気、ぼんやり感
- めまいやふらつき
- 集中力の低下、記憶が曖昧になる
- 光や音に敏感になる
- 気分の変動、不安感やイライラ
- 寝つきが悪い、寝ても疲れが取れない
こうした症状が続く場合、脳の神経ネットワークが過敏な状態になっている可能性があります。
スポーツにおける脳震盪と国際基準|“If in doubt, sit them out”
特にスポーツ現場では、脳震盪は見逃してはならない重大な問題とされています。
世界中のスポーツ医学の専門家がまとめた**「スポーツ脳震盪に関する国際コンセンサス(Amsterdam 2022)」**では、以下の対応が推奨されています:
【スポーツ脳震盪 国際基準の主なポイント】
- 脳震盪が疑われたらその場で競技を中止
- 当日の競技復帰は禁止(“Same Day Return”はNG)
- 脳震盪は画像で見えない機能障害。症状の経過観察が最重要
- **段階的な競技復帰(リカバリープロトコル)**が必要
- 10代以下の選手は慎重に対応。回復に時間がかかる傾向
「If in doubt, sit them out」=迷ったらプレーさせない
これは世界の共通認識です。
こうした基準は、日本のサッカー協会やラグビー協会、教育現場などでも導入されています。
脳震盪が起きたときの正しい対処法
🧠脳震盪の疑いがあるときの対応フロー
- すぐに活動を中止させる(症状がなくても)
- 医療機関(脳神経外科など)での評価を受ける
- その日は絶対に競技や運動に復帰させない
- 日常生活にも注意し、無理な画面使用・長時間の勉強を控える
- 回復後も段階的に日常生活・運動を再開
🏥画像検査で異常が出ない場合でも…
脳震盪は「構造の損傷」ではなく「機能の混乱」。
だからこそ、「異常なし」と言われても症状があるならケアが必要です。
当院の脳震盪ケア|神経へのアプローチで自然な回復を支援します
当院では、脳震盪後の神経系の乱れを整えるための専門的なケアを行っています。
画像検査や投薬ではアプローチできない、機能の回復・調整を目的としています。
📌ケアの特徴
- 振動刺激:耳後部・後頭部などへの微細な刺激で、前庭・脳幹系を穏やかに活性化
- 感覚統合:視覚・バランス・体性感覚を組み合わせ、神経系の統合力を回復
- 呼吸と自律神経へのアプローチ:交感神経優位な状態からのリセットを促します
こんな方におすすめです
- 軽い衝撃のあと「なんとなく不調」が続いている
- 医療機関では異常なしと言われたが、調子が戻らない
- 頭痛やめまい、疲労感が長引いている
- 子どもの集中力や感情のコントロールが不安定になった
- スポーツ復帰前に神経機能を確認したい
まずはお気軽にご相談ください
脳震盪は早期発見・早期ケアが回復の鍵です。
小さな違和感でも、「身体が出しているサイン」かもしれません。
🔍まとめ|脳震盪ケアのポイント
- 脳震盪は軽視されがちな神経障害。症状がなくても注意が必要
- 国際基準では当日の復帰は禁止、段階的回復が推奨されている
- 画像検査で異常がなくても、機能の乱れは残ることがある
- 専門的ケアによって神経系の自然な回復を後押しできる
- スポーツ現場・成長期の子ども・大人の転倒後にも対応可能
スポーツ脳震盪 国際合意声明(Amsterdam 2022・英語)
SCAT5 日本語版(日本ラグビーフットボール協会)