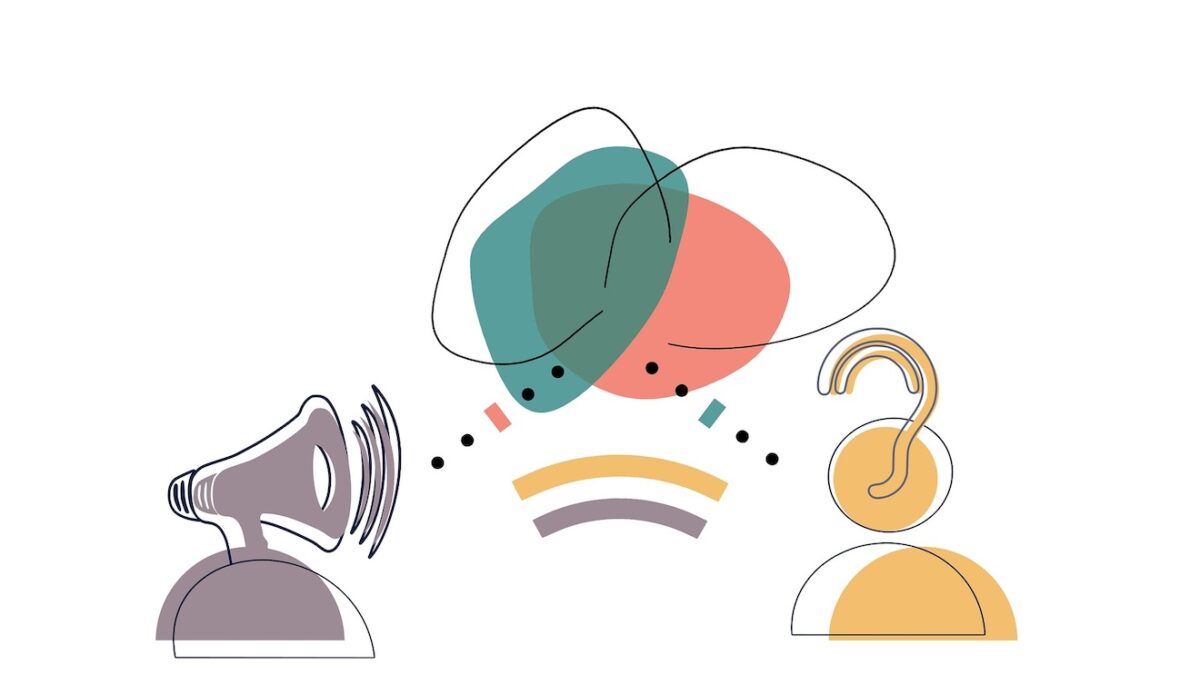整形外科や整骨院などで「骨が変形していますね」と言われると、多くの方が「だから痛いのか」と納得されます。
しかし、「骨の変形=痛み」という考え方は、半分は正解で、半分は誤解です。
実は、骨の変形は単なる「形の問題」ではなく、骨代謝(骨の新陳代謝)や機能変化の一側面として理解する必要があります。
本記事では、そうした骨変形と痛みの関係について、科学的な視点を交えてわかりやすく解説します。
骨の変形は、機能低下や骨代謝の変化の“ひとつのサイン”
まず前提として骨は常に「壊されては作られる」というリモデリング(再構築)を繰り返している組織です。この過程は**「骨代謝」**と呼ばれ、加齢やホルモンバランス、炎症、荷重のかかり方などに影響されます。
この骨代謝がアンバランスになると次第に骨の構造が変化し、レントゲンやMRIで“骨の変形”として可視化されるようになります。
特に股関節や膝関節など荷重が集中しやすい部位では、変形が周囲の関節軟骨や靱帯、筋肉にまで影響を及ぼすことがあり、結果的に関節の機能低下を招く場合があります。
つまり、骨の変形は「骨そのものの問題」というよりも、“骨の機能変化・代謝変化”の一表現であり、これが痛みの一因となることは確かです。
でも「骨が変形している=必ず痛む」わけではない
一方で、骨が変形していても、まったく痛みを感じていない人は大勢います。これはさまざまな研究からも示唆されています。
🔍 研究データより
たとえば、以下のような研究があります:
- Lawrence et al., 2008(Framingham Osteoarthritis Study)
60歳以上の人を対象にした股関節のX線検査において、画像上で変形性股関節症の所見がある人のうち、約50%が無症状であったと報告されています。 - Hunter DJ et al., 2011(BMJ)
膝関節でも同様に、画像上で明らかな変形があっても痛みがない人が多数存在することが確認されています。
このように、骨の変形はあくまで「構造的な変化」にすぎず、「痛みの有無」を直接決定するものではないことが明らかになっています。
🧠 痛みは「構造」だけでなく、「神経」や「心理」も関係する
人間が痛みを感じる仕組みには、以下のような複数の要素が関わっています:
- 神経の興奮状態(中枢感作など)
- 筋膜や靭帯の緊張
- 血流障害
- 心理的要因(ストレス、不安、注意の向け方)
つまり、骨が変形していても、神経系が過敏になっていなければ痛みは生じにくく、逆に骨に大きな異常がなくても痛みを強く感じるケースもあるということです。
「骨の変形」は変えられない。でも「機能」は改善できる
一度生じた骨変形は、基本的に自然には元に戻りません。ですが、それを悲観する必要はありません。
- 適切な運動療法や筋力トレーニング
- 姿勢や歩行の改善
- 振動療法や温熱療法による神経系の調整
などによって、機能を保ちながら痛みをコントロールすることは十分可能です。
まとめ:骨変形を「静止画」でなく「動き」で捉えよう
| 誤解 | 実際のところ |
|---|---|
| 骨が変形しているから痛い | 骨の変形は一因であり、痛みの直接原因とは限らない |
| 骨が元に戻らないからもう無理 | 機能の改善は十分可能。痛みもコントロールできる |
レントゲンやMRIなどの画像はあくまで「静止画」にすぎません。大事なのは、**日常生活における「動きの質」や「神経系の状態」**です。
骨の形だけを見て将来を悲観せず、今できる身体のケアを積み重ねることで、より快適な生活が実現できます。